
七夕飾りや願い事を吊るした笹は、七夕を過ぎたらどう処分していいか困ってしまうかと思います。
笹の処分方法は主に3つあって、一番手軽なのは燃えるゴミの時に出してしまうことです。
また、短冊は捨ててもいいのですが、とっておきの保存方法があるんですよ。
この記事では、七夕飾りや笹の処分方法について、詳しくお伝えしていきますね!
七夕飾りや笹はどうやって処分すればいい?処分方法は3パターン!

笹は魔除けとして使われ、竹は高く伸びるため神様の目印とされています。
そんな神聖なものを一体どうやって処分すればいいの!?と迷ってしまいますよね。
七夕飾りや笹は、川や海に流して神様に持ち帰ってもらうというのが正式な処分方法なんです。
これを「七夕送り」といって、昔は実践されていましたが、
環境問題に引っかかってしまうので、今ではほとんど行われていません。
現在のメジャーな処分方法は以下の3つです。
1. 神社でお焚き上げをしてもらう
神聖なものを自分で処分するのは気が引ける…となれば、神社にお願いしてしまいましょう!
神社で行ってもらうなら、なんだか安心できますもんね。
ただ、お焚き上げを行っている神社と行っていない神社があります。
近くの神社がお焚き上げを行っているかどうか、事前に確認してから持ち込むようにしてくださいね。
2. 敷地内で焼却する
近くにお焚き上げをしてくれる神社がないと、大きな笹を持っていくのは大変ですよね。
神社でお焚き上げをしてもらわなくても、敷地内で燃やしてしまうという手があります。
七夕飾りや笹を燃やして、その煙が空に上っていく様子を子どもたちと眺めるのもいいですよね。
「これで願い事がお星様に届くよ」なんて言ってあげれば、子どもたちも喜んでくれることでしょう。
ただ、焼却するに当たって、
・近所からクレームが来ないか
というのを十分に調べたり、検討したりする必要があります。
個人で判断せず、他の先生に確認してから実施するようにしましょう。
3. 燃えるゴミとして出す
近くにお焚き上げをしてくれる神社がなく、敷地内での焼却もできそうにない場合は、燃えるゴミとして出してしまうのがオススメです。
一番手っ取り早いので、時間と手間をかけずにサッと処分できるのがいいですよね。
笹は可燃ゴミとして出せるので、ハサミでゴミ袋に入る大きさに切ってくださいね。
ただ、さすがにそのままゴミとして出すのは、なんだか罰当たりのような気がしてしまいますよね。
そんなときは、白い紙に包んでください。
古くから、白い紙は神聖で、浄化する力があるといわれてきました。
なので、切った笹は白い紙で包んでからゴミ袋に入れれば、きちんと浄化をしてくれるので、燃えるゴミで出しても大丈夫ですよ!
七夕飾りは一夜飾りが原則なので、7月7日の夜、遅くても8日には処分するのが理想です。
あなたや幼稚園にあった処分方法を実践してみてくださいね。
短冊はどうする?一般的な処分方法やオススメの保存方法はコレ!

短冊は願い事を書くので、そのまま捨てていいのか悩みますよね。
実は、短冊を含めた七夕飾りというのは、本来残しておかないものなんです。
元々は笹といっしょに川や海へ流していましたからね。
なので、捨ててしまって大丈夫なんです。
ただ、その捨て方ですよね。
短冊の処分方法は、笹と同様の3つです。
・神社でお焚き上げをしてもらう
・敷地内で焼却する
・燃えるゴミとして出す
燃えるゴミとして出す場合、笹と同じように短冊も白い紙で包むと良いですよ。
ただ、短冊を処分せずに残しておくというのも手です。
せっかく幼稚園で3年間行う七夕なのですから、一人一人ファイルや台紙などを作って、3年分の短冊をまとめておいてあげると見返せますよね。
年少さんの頃と年長さんで願いがどれだけ変わったのか、また、3年間ずっと同じことを願っていたなど、後で先生や家族と見返すのも楽しいかと思います。
年長時の七夕が終わったとき、または卒園式の日など渡す日を決めてあげると良いでしょう。
まとめ

七夕の行事を行うのは楽しいですが、七夕飾りや笹の処分方法は悩みの種ですよね。
今回お伝えした3つの方法のどれかで良いので、合う方法を選んでください。
迷ったら燃えるゴミで問題ないですからね。
私は、七夕で使う七夕飾りと笹は毎年ホームセンターで買うのですが、その都度燃えるゴミとして捨てていますよ。
何事も後片付けのことを考えると億劫になりがちですが、処分方法を先に決めておいて、七夕は園児たちと楽しく過ごしてくださいね!
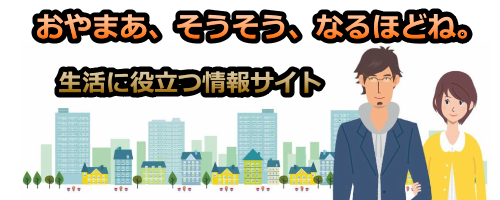
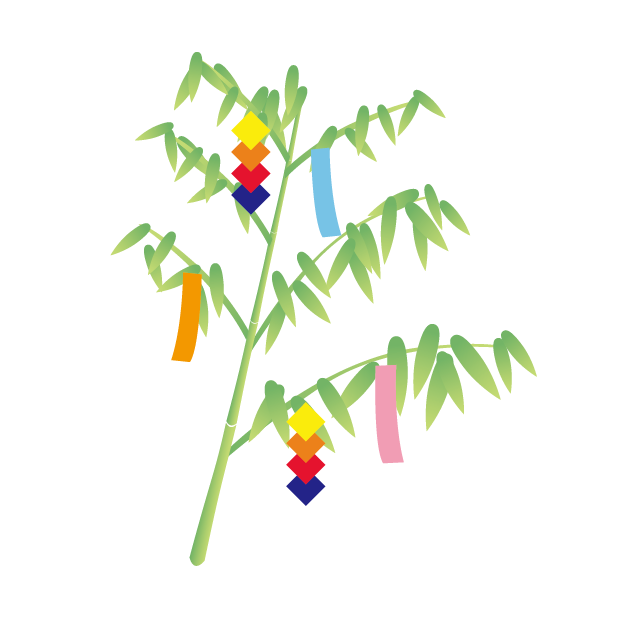







コメント