
文化の日は11月3日。
この休日の由来について、しっかり考えたことがありますか?
もし、お子さんがあなたに尋ねたとしたら、答えてあげることはできますか?
「このお休みの日は、何か意味のある日なの?」
私には、説明できそうにありません。
毎年確実にやってくるのに、気にも留めていない文化の日。
子どもにも分かりやすく説明するには、まずは大人がしっかり知っておくべきですね。
しっかりおさらいして、次の文化の日にはちゃんと教えてあげたいですね。
今からでも、遅くはないですよ!
元は違う祝日だった!?11月3日の本当の意味とは?
秋も深まってくる11月3日の祝日…。
実は、この日は元々別のことを祝う日だったのはご存知ですか?
正確には、「誰か」の誕生日にあたる日なのです。
その「誰か」とは、明治天皇です。
明治天皇が崩御され、大正そして昭和へと時代が移り変わった頃です。
国民の中で、明治天皇のお誕生日を祝日として残そうという動きがありました。
そして生まれたのが、「明治節(めいじせつ)」という祝日なのです。
その後の20年間、11月3日は明治節のままでした。
では、一体どういう流れで、私たちの知っている「文化の日」となったのでしょう。
明治節が出来て20年後、日本は既に戦後の時代をむかえていました。
戦争に負けた日本は、アメリカの手によって大きく変えられようとしていました。
「天皇」という存在も、その変化のために排除を迫られたもののひとつです。
アメリカは、また日本国民がその存在の元に団結するのを恐れていました。
あがめる存在をなくしてしまうことで、日本が弱くなるのを狙っていたのです。
そのため、明治天皇のお誕生日にあたる11月3日の祝日も、消されそうになりました。
それを阻止しようと誕生したのが、文化の日なのです。
明治節を守るために考えた結果、日本国憲法の公布日を「わざと」その日に当てました。
そして11月3日は「日本国憲法の公布されたことを祝う日」として、残ることになったのです。
ちなみに、「公布日」とは●●という法律を作りましたということを「公にした日」を指します。
5月の「憲法記念日」は、日本国憲法が法律として動き出した日を意味します。
ちょっとややこしいですね。
文化ってそもそも何?もっと具体的に文化の日を解説!

文化の日の成り立ちについては、少なからず分かっていただけたのではないでしょうか。
「じゃあお母さん、文化って何なの?」
こんな質問が飛んできたら、私はやはり即答することができません…。
「自由と平和を愛し、文化を進める」
これは、言わば文化の日のキャッチコピーです。
そういうことを頭に置いて、文化の日を過ごしましょうというわけですね。
「文化」とは何か?
もはや当たり前すぎて、それが何なのかなんて考えたこともないですよね。
何かと聞かれても、はっきりしたことはなかなか言えない。
文化って、ぼんやりとした不思議なものです。
スポーツは、体の運動です。
野球だとかサッカーだとか、いろいろありますね。
文化というのも実は同じようなものなんです。
文化とは、芸術や哲学、あるいは科学といった、精神面での活動のことを言います。

芸術の秋などと言いますが、文化の日が11月にあることを考えると、それも納得ですね。
もし、あなたが明日の食事もできないほど困っていたらどうでしょう。
明日生きていられるか分からないほど、危険なところにいたとしたら?
人は、そういう場面で「文化」のことについて考えるでしょうか?
文化はというものは、実はとても贅沢なものなのかもしれません。
日々の生活が当然のように保証されていて、他のことを考える余裕があるからこそのものなのです。
「自由と平和を愛し、文化を進める」との願いを込めた日は、戦後間もない頃に生まれました。
混乱の中で人々が目指したものは、今の私たちにちゃんと受け継がれています。
私たちは平和な国であらゆる自由を持ち、多くの文化を作り上げてきたのですから。
まとめ

「ねえお母さん、文化の日というのは、何か意味のある日なの?」
そう聞かれたとき、もうまごまごしてしまうことはなくなりそうですか?
自分が理解したつもりでも、子どもに分かりやすく説明するのは難しいことなんですよね。
でも一度、簡単な言葉で説明してあげてみてください。
その生活の中から、文化というものが生まれてくるのだということ。
そして今のこの毎日を、これからも守っていってほしいこと。
他の言葉でなかなか置き換えられないこともあります。
無理はせず、それはそのまま伝えてもいいんじゃないでしょうか。
子どもが大きくなった時、ふと理解できるタイミングがやってくるはずです。
それを願って、お子さんと文化の日を楽しんでみてくださいね。
合わせて読みたい記事はこちら!
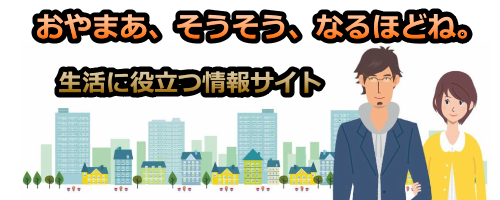



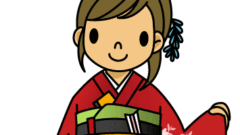

コメント