
「秋分の日」が何月何日で、何の日か正確に説明できますか?
実際に私はちょっと自信がありませんでした。
何となくはわかっていましたが、調べてみて「えっ?」と思ってしまうことのほうが多かったです。
今回は「秋分の日」の意味と由来について詳しく調べてみました。
是非これを読んで堂々と「秋分の日」を語ってください。
「秋分の日」日にちは決まっていない??
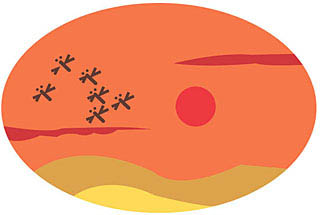
「秋分の日」とは、日本の国民の祝日のひとつです。
辞書などで調べてみると、
祝日法により天文観測による秋分が起こる秋分日が選定され休日とされる。
と、書いてあります。
この文面だけ読むと、何だか少し専門的で難しい内容のような感じがしますね。
続きを読むと、
通例では、9月22日、9月23日頃のいずれか1日を指す。
とも書いてあるのです。
そうです、秋分の日は毎年同じではないのです。
秋分の日の最大の特徴は、
「昼と夜の長さが等しくなる日」であるということです。
このことに関しては、子どもの頃理科の授業で習った!という方も多いのではないでしょうか?
祝日は基本的に毎年同じ日のはずですが、なぜ秋分の日は毎年日にちが変わるのでしょう?
秋分とは?

二十四節気とは季節の変化の暦で、季節や天候に左右されやすい古くから農業の目安になってきました。
昔むかし、農家では春分の日の頃に農作業を始めて、秋分の日の頃に終えていたのだそうです。
秋分の日は、太陽の通り道である「秋分点」と呼ばれる位置を太陽が通過する日のことを言います。
この「秋分点」を通過した日が「秋分の日」ということになります。
昼と夜の長さが等しくなる日と言われていますが、太陽が通過する時間には若干のずれが生じます。
毎年多少の誤差があるそうですが、平均して15分ほど昼の時間の方が長いのだそうです。
秋分の日の意味と由来について

「秋分の日」の前後は、世間では「お彼岸」の時期にあたりますね。
日本に仏教が普及してからは、真西に極楽浄土があるという教えにより、お彼岸の頃は太陽が真西に沈むことから、この世(現世)とあの世(彼岸)が通じやすくなると考えられていました。
そのため、この時期にご先祖様の供養をするようになったと言われています。
明治11年から昭和22年までは「秋季皇霊祭・しゅうきこうれいさい」として歴代の皇族の霊を祀る宮中の儀式を行う日で、祭日とされていました。
その後、昭和23年に、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という趣旨のもと、国民の祝日に関する法律によって祝日として制定され、現在に
至ります。
今年の秋分の日は?
2019年の秋分の日は9月23日(月)です。
秋分の日は、国立天文台が発行する「暦象年表」をもとに政府が決定しています。
毎年(前年の)2月1日に交付されています。
太陽が秋分点を通過する日がその年によって異なるため、毎年の発表となるそうです。
他の祝日のように日にちの固定ができない祝日というわけですね。
ちなみにこの先の秋分の日は、21世紀中は22日か23日のどちらかになるのだそうですよ。
秋分の日は計算できる??

秋分の日が22日なのか23日なのかは、その年がうるう年かどうかで確認できます。
うるう年の時は9月22日、うるう年ではない年は9月23日となります。
2019年はうるう年ではないので9月23日というわけですね。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
秋分の日を9月22日か9月23日だと思っていたのは、あながち間違いではなかったことを知って安心しました。
しかし、秋分の日がこんなに奥深いのもだとは思ってもみなかったのでとても勉強になりました!!
農業、仏教、皇室、国立天文台・・・など、様々なキーワードが出て来ましたね。
今年の秋分の日は9月23日です。
お彼岸にはご先祖様の供養をしっかりして、今日という日を迎えられる幸せに感謝しましょう。
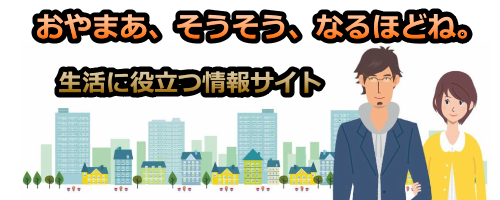






コメント