
あなたは、毎年七草粥を食べますか?
ご家庭によっては、七草をお粥ではなくお雑煮にしていただくところもあるようですね。
年末から年始にかけて、私たちは美味しいものをついつい食べすぎてしまいます。
今にも悲鳴をあげそうな胃をいたわってあげよう。
七草粥には、そんな意味もあるのです。
とても理にかなった話ですね。
でも、どうして七草というものが入るのでしょうか。
お粥にするのは、何か意味があるの?
疑問に思った時こそ、新しいことを知るチャンスです。
七草粥の意味や由来について、一緒に覚えませんか?
そもそも七草とは?七草粥の習慣は中国からやってきた!?

七草粥に入る七草を、あなたはすべて言えますか?
これらは「春の七草」と呼ばれ、七草粥はこれを刻んで入れたお粥です。
「すずな、すずしろなんて聞いたこともない植物だ!」
これらは実はとても日常的な野菜なんです。
すずなはカブのこと
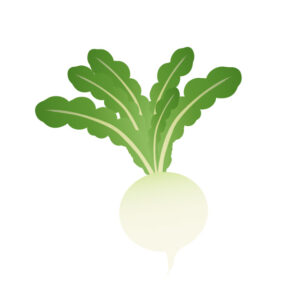
すずしろは大根のことです。

その他の野草も、子どものころ原っぱで見たことあるようなものばかりです。
七草粥には、昔からいろいろな思いが込められていました。
まず、あらゆる邪気や病気から体を守ってくれるように。
先ほども触れましたが、疲れた胃腸をいたわってくれるように。
また、冬場には野菜の栄養が不足しがちです。
それを補うという意味でも、七草粥は重宝されてきたのでしょう。
何せ7種類もの青菜が入っているのですから、栄養はありそうですよね。
そういった意味を持つ七草粥ですが、どうして1月7日に食べるようになったのでしょうか?
1月7日は「人日の節句(じんじつのせっく)」というものにあたり、これは、昔の中国から伝わったもの。
当時はお粥というより、7種類の野菜を入れたとろみのついた汁ものだったようです。
これをこの日に食べて、無病息災を祈願したと言われています。
また、日本の古くからの習慣として、「若菜摘み」があります。
これを食べると、病気や邪気が払われると考えられていました。
唐の時代の習慣と若菜摘みが一緒になって、今の七草粥の習慣になったと言われているのです。
新しい年に新しく生まれた植物の命をいただくというのは、なるほど、とても神聖な感じがしますね。
もはやお粥でない?ここまで違う!1月7日に食べるもの!

さて、ここまでは七草粥の意味や由来について見てきました。
ところで、この習慣は地方によってかなりの差があるのをご存知でしたか?
縦に長い日本という国です。
ところ変われば、七草粥も様々ということ。
いくつかピックアップしてみましょう。
●東北地方
雪深い東北では、とてもじゃないけれど雪の間の若菜を摘めません…。
なので、七草なしのお粥や、集められるもので作ったものが多いようです。
無病息災を祈る行事で無理して七草を集めて、風邪でも引いたら無意味ですよね。
また、山形県のある地域はとてもユニークです。
神前に供えたおにぎりに、野菜や昆布、干し柿を加えてお粥を作るのだとか。
●東京都
主に、スーパーや八百屋などで購入した七草を使っての七草粥です。
とりあえず手に入るものだけで作る、というのも特徴のようです。
何だか、東京らしいと思うのは私だけ?
その中でも変わっているのは、品川区は大崎というところ。
ありあわせの七草粥に、白砂糖をかけて食べるのだそうです!
●関東地方
お粥といえば塩味?
神奈川県の相模原市は、お醤油味のお粥だそう。
●北陸地方
富山県のとある地方では、1月7日ではなく、2月15日に食べます。
しかも、食べるのは七草粥ではなく、「あかぞろ」と呼ばれるおぜんざい。
また、石川県では汁もの(ぜんざい)を食べるところが多いようです。
●関西地方
大阪府では、七草や青菜、餅を入れた赤味噌仕立ての雑炊を食べるところがあるそう。
本来、関西の食習慣では白い米味噌が主流なので不思議ですね。
ちなみに、赤味噌は豆味噌で、東海地方に多いです。
●中国・四国地方
岡山県のある町では、七草粥にスルメを入れたものを食べるそうです。
ちょっと変わっているのは、香川県は東かがわ市。
こちらはお粥でもお雑煮でもなく、ほうれん草の白和えをいただくようです。
ほうれん草は、神前に供えたものを使います。
同じく香川県の小豆島では、青菜と油揚げを味噌で和えたものを食べるそうです。
徳島県の鳴門市では、七草の和え物を。
味付けは、白味噌、ゴマ、砂糖とシンプルなもの。
中国・四国地方は、お粥や汁ものでないものが多い印象です。
●九州地方
長崎県のとある地方では、七草雑炊のほか、ありあわせの野菜を入れた炊き込みご飯を食べる所があるようです。
さらにユニークなのは、作った雑炊は神仏に供えた後、庭などの果樹に塗り付ける風習もあるのです。
これによって、豊作を願うのだそう。
●沖縄県
沖縄の食文化には独特のものがあります。
多くの地域では雑炊のようなものが食べられていますが、糸満市は変わっています。
「たーんむ」という里芋を煮て、砂糖で練ったものをいただくそうです。
まとめ

いかがでしたか?
七草粥について、「ほほーう」となる新しいことは見つかったでしょうか。
1月7日の七草粥に深い由来があることは驚きでした。
ちなみに、七草は前日の6日に、用意していたものを細かくしておきます。
そして翌日に炊いたお粥に混ぜることから、朝食でいただくのが正解のようですね。
日本全国がお粥を食べているわけではないことは知っていましたか?
私は知らなかったので、とても興味深かったです。
「みんなこういうものだと思ってたけど、うちだけだったの!?」
別の驚きを隠せない場合もあったかもしれませんね。
年が明けても、冬はいよいよ厳しくなってきます。
温かい七草粥をみんなでいただいて、病気なんかに負けないようにしたいですね!
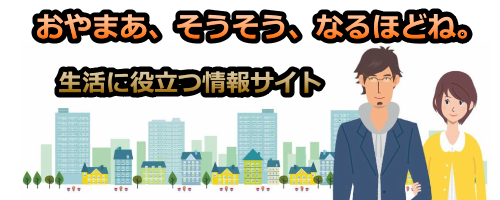




コメント